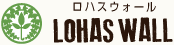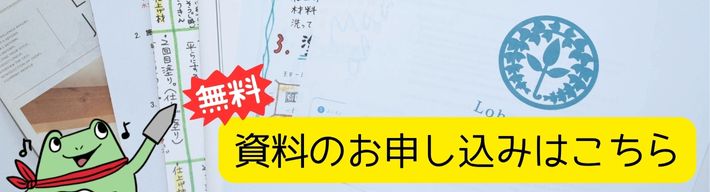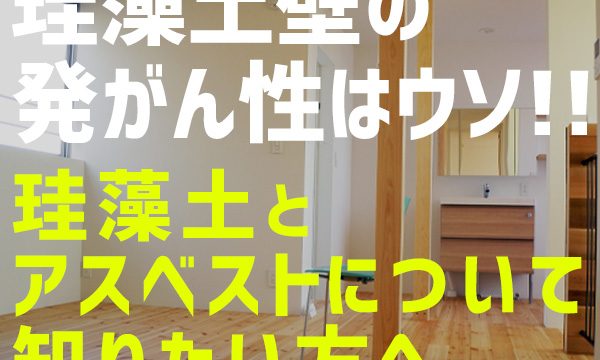今回は、漆(うるし)と漆喰(しっくい)の違いについて説明します。
【この記事に書いてあること】
・漆喰とはなんなのか?メリットやデメリットについて
・自然素材 漆喰の施工事例
・漆喰と漆の違い
もくじ
漆喰とはなんなのか?

漆喰とは消石灰を主原料とした自然素材の壁材で、調湿力、消臭力、抗菌性、耐久性などに優れた壁材です。
このような漆喰の性質から、漆喰をお部屋に塗ることで次のようなメリットがあります。
・お部屋の湿度を調節してくれる
・生活臭などの臭いを消臭してくれる
・シックハウス症候群の対策になる
漆喰は、内装の壁の90%以上で使われているビニールクロスなどに比べて、材料費や施工費が高いというのがデメリットです。
ただし、体にも優しい自然素材で、様々な性能を持つことから、漆喰は人気の壁材となっています。
関連記事:漆喰とは何なのか?用途、施工実例、メリット・デメリットについて

漆喰を使った施工事例をご覧ください

| 広さ | 1,100,000円(材料、工賃込み) |
| 費用 | 120平米 |
| 築年数 | 新築 |
| 施工方法 | 職人による施工 |

| 広さ | 440,000円(材料、道具、インストラクター派遣込み) |
| 費用 | 130平米 |
| 築年数 | 新築 |
| 備考 | DIY |

| 広さ | 24平米 |
| 費用 | 60,000円(材料、道具、諸費用込み) |
| 築年数 | 15年 |
| 備考 | DIY |

| 費用 | 約60,000円(漆喰材料費+道具) |
| 広さ | 14平米 |
| 築年数 | 江戸時代 |
| 備考 | DIY |

| 費用 | 1,100,000円(材料、道具、インストラクター派遣込み) |
| 広さ | 340平米(36坪) |
| 築年数 | 新築 |
| 施工方法 | DIY |
漆喰のメリットについて
漆喰には次のようなメリットがあります。
・お部屋の湿度を調節してくれる
・生活臭などのニオイを消臭してくれる
・シックハウス症候群の対策になる
それぞれについて説明します。
漆喰を使うメリット:お部屋の湿度を調節してくれる

漆喰にはお部屋の湿度を調節してくれる調湿効果があるので、年中通して快適で過ごしやすい環境を作ることができます。
その理由は、漆喰の原料は細かな穴がたくさん空いている「多孔質」といわれる構造になっているため、空気中の湿気を吸い、空気が乾燥すれば空気中に水分を放出してくれます。
この漆喰の調湿効果によって湿気の多い時期にはカビやダニ等の発生を抑制することにも繋がります。
実際に、ロハスウォールで漆喰を塗ったお客様からも、
「漆喰の優れた調湿力のおかげで、エアコンの温度が1〜2℃上げても快適に過ごせるので電気代の節約になった」
「快適な湿度の空気だから夜中寝ているとき一度も起きず熟睡できるようになった」
といった声をいただいています。
漆喰を使うメリット:生活臭などの臭いを消臭してくれる

漆喰は消臭力も高く、内装の壁に塗ることでお部屋の生活臭や、トイレや玄関の嫌な臭いを消臭してくれます。
漆喰は強アルカリ性(ph12.6)の性質をもっていて、漆喰が吸い込んだニオイ成分を含んだ空気が、漆喰の強アルカリ性によってニオイ成分が無臭の成分に分解されるため、高い消臭効果に繋がっています。
実際に、ロハスウォールで漆喰を塗ったお客様からも、トイレのニオイや食べ物のニオイ、玄関やペットなどの生活臭が気にならなくなった、中古の家を買う方には「前の居住者の匂いが消えた」という声をいただいています。
漆喰を使うメリット:シックハウス症候群の対策になる

漆喰は調湿力消臭力の他に、抗菌性にも優れています。
また、この漆喰の抗菌性は近年、問題になっているシックハウス症候群の対策にもなります。
先ほども説明したように、漆喰は強アルカリ性(ph12.6)の性質を持っているため、ニオイ成分を無臭の成分に分解してくれるだけではなく、シックハウス症候群の原因物質を吸収し分解して、無害化していく効果があります。
また、この漆喰の抗菌性はコロナ禍の今、さらに注目されていて、漆喰の強アルカリ性は風邪ウィルス、インフルエンザ、エボラ、新型コロナなど他多数のウイルスの働きを弱める効果があり、注目を集めています。
その他の漆喰のメリットについてはこちらで詳しく解説しています。
>漆喰のメリット、耐久性と断熱性、防火性、防音効果をプロが解説します。

漆喰のデメリットについて
漆喰のデメリットは壁紙に比べて金額が高いことです。
漆喰
材料費:1,000〜3,000円/㎡
施工費:7,000〜15,000円/㎡
ビニールクロス
材料費:500〜1,500/㎡
施工費:900〜1,700円/㎡
内装の壁の90%以上で使われているビニールクロスなどの壁紙に比べて、平米単価は最大で材料費は6倍、施工費は16倍ほど漆喰の方がビニールクロスより高いです。
漆喰はビニールクロスにはない調湿力や消臭力、抗菌性といった性質があり、原料に自然素材である消石灰を使用しています。
そのため、漆喰はビニールクロスに比べて、1平米あたり材料費が約1,000円、施工費が約6,000円ほど高くなります。
例えば、6畳の部屋を漆喰壁にする場合、漆喰を塗る面積がおおよそ30㎡となるため、漆喰とビニールクロスとでは、漆喰の方が材料費で3万円、施工費で約18万円ほど高くなります。
このように漆喰は、原料に自然素材である消石灰を使用していたり、ビニールクロスのような壁紙のように張って終わりではなく、職人によってコテを使って施工する必要があるため、工期も長くなり費用が高い代わりに、調湿力や消臭力、抗菌性などの壁材として優れた機能をもっています。
漆(うるし)と漆喰(しっくい)の違い
素材の違いについて
| 原料 | |
| 漆喰(しっくい) | 消石灰 |
| 漆(うるし) | ウルシオールの天然樹脂 |
漆喰とは、先ほども説明したように主原料を消石灰(水酸化カルシウム)とした壁材です。
主原料である消石灰は、石灰石を焼いて水を加えて作られますが、この石灰石はサンゴ礁がルーツとなっています。
一方、漆(うるし)とは、わかりやすく言うと「天然のコーティング剤」です。
ウルシ科のウルシノキやブラックツリーから採取した樹液を加工した、ウルシオールを主成分とする天然樹脂から作られる塗料のことをいいます。
昔、漆は食用にもなっていて、漆の新芽は食べることができ、味噌汁や天ぷらにするとえぐみもなく美味いそうです。

漆喰と漆では同じ「漆」という字を持つことから、漆喰と漆は関係があるように思われる方が多いのですが、このように「漆喰はサンゴ礁をルーツとした消石灰」、漆は「ウルシオールを主成分とする天然樹脂」であり、全く違うもので、その用途も異なります。
次に、漆喰と漆の用途の違いについて説明します。
用途の違い
| 用途 | |
| 漆喰(しっくい) | 壁材 |
| 漆(うるし) | 塗料、漆器 |
漆喰は、調湿力や消臭力、抗菌性など、様々な性能をもつ壁材として使われます。
漆喰は4000年前(縄文時代後期)の、千葉市の大膳野南貝塚で調理施設として使われていたとされる炉穴内部や周辺の床に厚さ1センチほど塗り固められた状態で漆喰が出土していて、現存しているものだと1200年前の高松塚古墳やキトラ古墳、平等院鳳凰堂の内部の壁、お城の壁にも使われていることでも有名です。
関連記事:現存天守12城や漆喰の遺跡をまとめてみた
漆(うるし)は、塗料や漆器などで利用されます。
漆の歴史は6800年前に、輪島塗りの産地から近い七尾市の三引遺跡から漆製品が発見されています。
日本では黒く輝く漆塗り漆器が伝統工芸として有名で、漆を表面に塗ることで器物が格段に長持ちする効果があります。

このように漆喰と漆では使用用途が昔から全く異なります。
漆喰と漆の違いについてのまとめ
漆喰も漆も同じ「漆」という字を含むため、近しい材料と考られることから、漆喰メーカーである私たちロハスウォールも「漆喰と漆の違いって何ですか?」という質問をよく受けます。
しかし、実際は素材や使用用途も全く違います。
| 素材 | 用途 | |
| 漆喰(しっくい) | 消石灰 | 壁材 |
| 漆(うるし) | ウルシオールの天然樹脂 | 塗料、漆器 |
漆喰は主原料を消石灰とすることから、壁に塗ることで次のようなメリット・デメリットがあります。
メリット
・お部屋の湿度を調節してくれる
・生活臭などのニオイを消臭してくれる
・シックハウス症候群の対策になる
デメリット
・壁紙に比べて金額が高い
この記事を読んで、漆喰についての疑問点やどの漆喰を塗ったらいいか分からないという方は気軽に、私たちロハスウォールにご相談ください。

0120-028-232 対応時間:月〜金 9:00〜18:00
メールでお問い合わせしたい方はここをクリック(24時間365日 問合せできます)
今回は漆喰のメリット、デメリットや漆との違いを中心に解説しましたが、もしロハスウォールのような自然素材100%でできた天然の漆喰についてもっと知りたい、触ってみたい、家の壁に塗ってみたいと思いましたら、お気軽に下記の資料請求(無料)や無料相談会、漆喰DIY教室にお越しください。
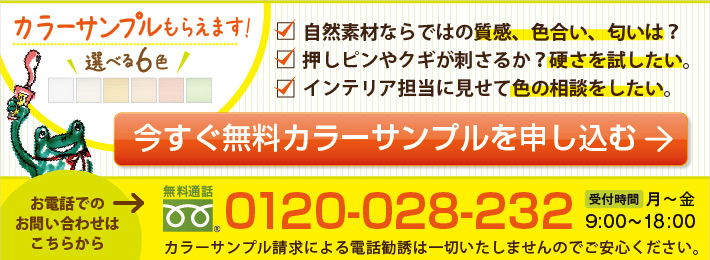
天然の自然素材100%漆喰を使ったリフォーム・DIYへの相談窓口(無料)
漆喰を使ったリフォームとDIYに関する相談や疑問の駆け込み寺で有名な、ロハスウォール【無料】漆喰リフォーム・DIY相談ダイヤルに連絡してください。
天然の自然素材100%漆喰を使ったDIYリフォーム教室
DIY初心者から大工さんや塗装屋さん、建築士までも学びに来る2,250人以上が参加した人気のDIY教室です。
実際に塗りながら学ぶことができ、プロがマンツーマンでプロ並みの完成度でDIYができるように指導します。
東京、大阪、仙台、岡山、名古屋、福岡で開催しています。